遊学モニターレポート
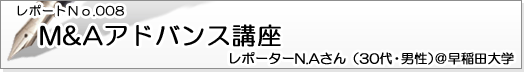
セカンドアカデミーを通じて講座を受講なさった方々に、実際の講座の様子をご紹介いただく、『遊学モニターレポート』、 第8回目の今回は東京の早稲田大学の「M&Aアドバンス講座」を受講なさったN.Aさんのレポートです。
旧京華小学校の3階部分が利用されています。そのため、建物は昭和初期に完成した建築物で随所に当時の面影が残っています。中は非常にキレイにリフォームされています。また、3階にはラウンジがあり、ここで授業時間になるまでコーヒーを飲んだり、本を読むことができます。尚、キャンパスは八丁堀駅、宝町駅というビジネス街にあるため、仕事帰りに気軽に受講することができます。授業自体も夜間に開講される講座が多いため、ビジネスマンが通いやすいようになっています。
早稲田大学エクステンションセンターのビジネス講座は、「内部統制」や「マーケティング」、「プロジェクトマネジメント」など日々の業務で役立つ実践的な講座から、「コーチング」、「ロジカルシンキング」、「自己分析」など具体的なスキルの講座まで多くのテーマで開講されています。講座のレベルも基礎~本格的な講座まで多くありました。
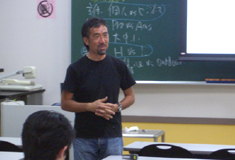

この講座は、「M&A入門講座」のアドバンス講座ということで、内容的には難しい講座でした。しかし、先生方は日頃M&Aに携わっている方々ですので、実践的な内容も学べました。周りの受講者の方々も、業務でM&Aに関わろうとされている方(30代~40代の方々)が多く、刺激にもなりました。
7月23日 |
M&Aにおける戦略(笠原英一氏) |
7月30日 |
企業価値評価(デューデリジェンス)の算出方法 (斎藤毅文氏) |
8月6日 |
バイアウト投資における企業価値の考え方(斎藤毅文氏) |
8月20日 |
M&Aの手法とM&Aの現場(能戸和典氏) |
8月27日 |
ポストM&Aの戦略(笠原英一氏) |
9月3日 |
M&Aにおける法律実務(雨宮 慶氏) |
 第5回は、みずほ情報総研客員研究員である笠原先生の講義でした。
第5回は、みずほ情報総研客員研究員である笠原先生の講義でした。講義の前半は、M&Aに置ける経営戦略について講義がありました。経営戦略を押さえることで「何故、経営判断としてM&Aを行うのか」ということについて再考するきっかけになりました。
 その後、「損益の試算」について学びました。
その後、「損益の試算」について学びました。笠原先生は「M&Aを行う際には【3年以内に単黒、5年以内に累計解消】というような、良くみかける計画を安易に作ってはいけない。」と言われました。確かに、損益をしようとすると、希望的観測も込めて下図のような試算をしてしまいがちです。
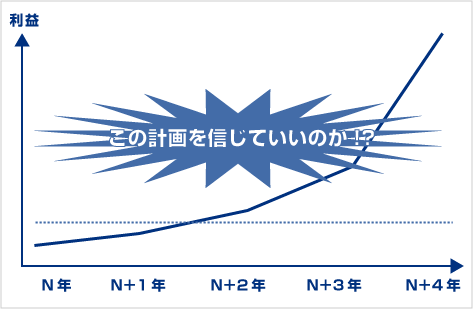 「分からないことが多くても、成功確率を高めるために損益シミュレーションをするので、市場規模×マーケットシェアを自分たちで考えて計算する必要がある」(笠原先生)
ということには、単純になるほどと思いました。
「分からないことが多くても、成功確率を高めるために損益シミュレーションをするので、市場規模×マーケットシェアを自分たちで考えて計算する必要がある」(笠原先生)
ということには、単純になるほどと思いました。【例】
例えば、インターネット通信事業者(A社)のM&Aを検討するとして、損益の試算をする際に、
潜在市場規模=関東戸建世帯数×ネット利用率×A社未導入率×移行率
というように試算できます。このようにブレークダウンすると、意外と小さいビジネスになることもあるようです(笑)。他にも業種や業態によって計算可能なため、色々な方法で計算してみようと思いました。
また、授業の後半では実際にM&Aのコンサルティングを行っている笠原先生らしく、統合の基本プロセスにおいて「統合準備段階で(既に方向性が決まっていても)中堅の優秀な人材を入れて一緒に経営戦略を考える必要なある」というような実践的なことをいくつか教えてもらいました。経営戦略が決まった後に社員に報告すると「勝手に決められたことだ。自分たちとは関係ない。」と思われて、統合がスムーズにいかないようです。
